百人一首の第16番は、作者 中納言行平(ちゅうなごんゆきひら)が詠んだ、別れの寂しさと都への未練を込めた歌として知られています。
百人一首『16番』の和歌とは
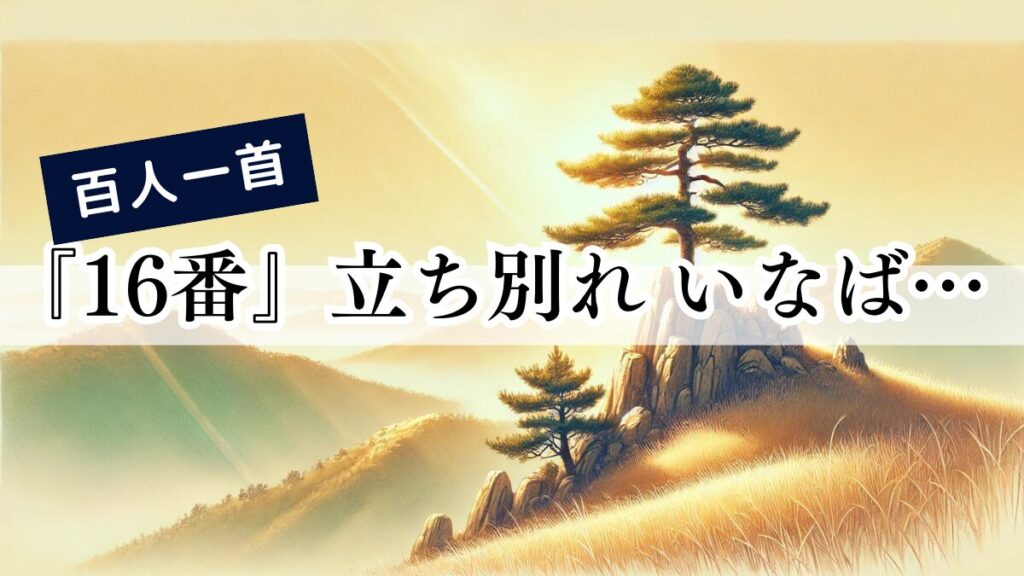
原文
たち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む
読み方・決まり字
たちわかれ いなばのやまの みねにおふる まつとしきかば いまかえりこむ
「たち」(二字決まり)
現代語訳・意味
あなたと別れて因幡(いなば)の国に行ったとしても、因幡の山の峰に生えている松のように、あなたが待っていると聞いたならば、すぐにでも帰ってこようと思います。

背景
百人一首の16番は、中納言行平(在原行平)が詠んだ和歌です。この歌は、彼が因幡(現在の鳥取県)へ国司として赴任する際に詠まれました。当時、地方への赴任は簡単に戻れない遠い旅路であり、都に残る人々との別れは切実なものでした。行平はその寂しさや都への思いを「稲羽山の松」に重ね、待っていてくれるならばすぐに戻ると詠みました。
また、この歌は単なる別れの歌ではなく、「待つ」と「松」の掛詞が使われており、優れた技巧も見られます。さらに、後世では「離れた人や動物が戻るおまじない」としても親しまれ、文化的な広がりを持つ歌となりました。このように、背景には都と地方の距離、別れの悲しみ、再会への希望が込められています。
語句解説
| たち別れ(たちわかれ) | 「たち」は接頭語で、意味を強調する役割を持っています。「別れ」は、因幡の国(現在の鳥取県)に赴任する際、都の人々との別れを指しています。 |
|---|---|
| いなばの山(いなばのやま) | 因幡国にある稲羽山(いなばやま)のことです。「往なば」(行ってしまう)という言葉と掛けて使われています。 |
| 峰(みね)に生ふる(おふる) | 「峰」は山の頂上や高い部分を指し、「生ふる」は生えている、つまり松が山の頂に生えている様子を表しています。 |
| まつとし聞かば(まつとしきかば) | 「まつ」は松の木と「待つ」という意味の掛詞です。「し」は強調の助詞で、「聞かば」は仮定条件を表し、「待っていると聞いたならば」という意味になります。 |
| 今帰り来む(いまかえりこむ) | 「今」は「すぐに」という意味です。「帰り来む」は「帰ってくる」という意志を表しており、「すぐにでも帰ってくる」という強い気持ちを示しています。 |
作者|中納言行平
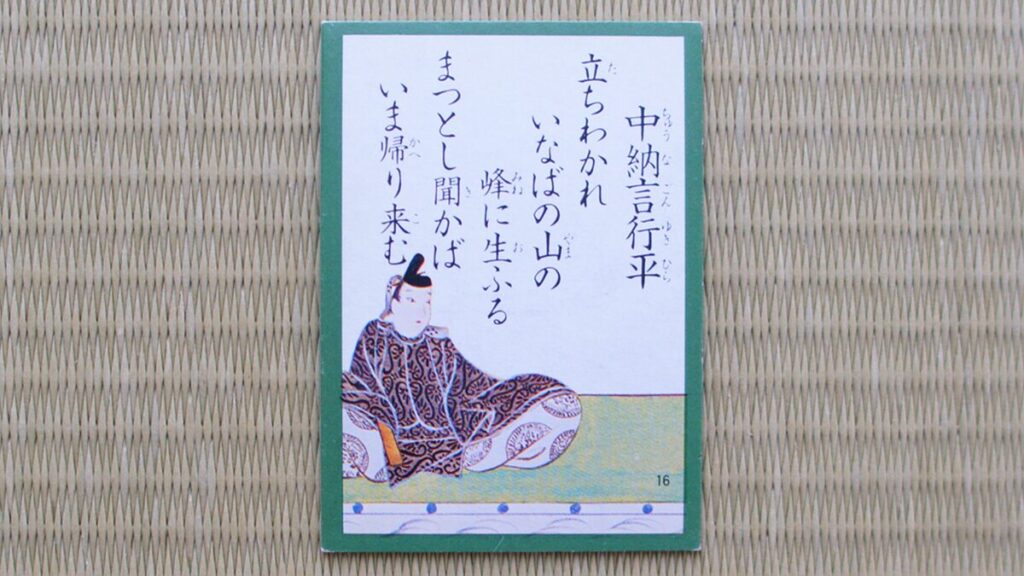
| 作者名 | 中納言行平(ちゅうなごんゆきひら) |
|---|---|
| 本名 | 在原行平(ありわらのゆきひら) |
| 生没年 | 818年 ~ 893年 |
| 家柄 | 平安時代の貴族で、平城天皇の皇子・阿保親王の次男。在原業平(百人一首17番歌の詠み人)の異母兄にあたります。 |
| 役職 | 中納言(朝廷の中級官僚)。その他、因幡守(いなばのかみ)や播磨守(はりまのかみ)など地方官を歴任 |
| 業績 | 政治的な役割を果たしつつ、63歳のときに奨学院(しょうがくいん)という学問所を設立し、教育に尽力しました。 |
| 歌の特徴 | 人々との別れを惜しむ心情や、都への強い思慕を歌に込めるのが特徴です。掛詞を巧みに用いた表現で、情景と心情を重ね合わせた技巧的な歌が多いです。 |
出典|古今和歌集
| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |
|---|---|
| 成立時期 | 905年(延喜5年) |
| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |
| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |
| 収録歌数 | 1,111首 |
| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |
| 収録巻 | 「離別(りべつ)」365番 |
語呂合わせ
たちわかれ いなばのやまの みねにおふる まつとしきかば いまかえりこむ
「たち まつと(立ち マット)」
百人一首『16番』の和歌の豆知識

ペットのおまじないとして使われる歌
特に、飼い猫がいなくなったときに、この歌を皿の下に書いて置いておくという風習が伝えられています。こうしたおまじないは、飼い主の再会への強い思いが、この歌の切ない別れの心情と重なるからかもしれません。
地方赴任の寂しさを詠んだ歌
当時、都を離れて地方に赴くことは、現在で言う転勤とは異なり、長期間にわたる別れを意味していました。そのため、行平の「すぐに戻って来たい」という思いは、都への強い未練や孤独感を表しています。
「稲羽山」は現代の鳥取県に実在する
この地は、古くから和歌に詠まれた名勝地で、行平以外にも、万葉集で有名な歌人・大伴家持(おおとものやかもち)もこの山を歌にしています。現在でも、稲羽山は自然散策の名所として知られ、行平の詩を偲ぶことができるスポットとして訪れることができます。
まとめ|百人一首『16番』のポイント
- 原文:たち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む
- 読み方:たちわかれ いなばのやまの みねにおふる まつとしきかば いまかえりこむ
- 決まり字:たち(二字決まり)
- 現代語訳:あなたと別れて因幡の国へ行くとしても、待っていると聞いたならすぐに帰ってこようと思う
- 背景:作者が地方赴任で都を離れる際に詠んだ別れの歌
- 語句解説①:たち別れ‐「たち」は接頭語で別れを強調する
- 語句解説②:いなばの山‐因幡の国にある稲羽山。「往なば」と掛詞
- 語句解説③:峰に生ふる‐松が山頂に生えている様子を表す
- 語句解説④:まつとし聞かば‐「松」と「待つ」の掛詞で「待つと聞いたならば」の意
- 語句解説⑤:今帰り来む‐「今」は「すぐに」を意味し、帰る意志を示す
- 作者:中納言行平(在原行平)
- 作者の業績:奨学院を設立し教育にも尽力した平安時代の貴族
- 出典:古今和歌集
- 出典の収録巻:離別(りべつ)
- 語呂合わせ:たち まつと(立ち マット)
- 豆知識①:ペットが戻るおまじないとして使われる歌‐皿の下に歌を書いて願掛けをする風習がある
- 豆知識②:地方赴任の寂しさを詠んだ歌‐都への未練と孤独感が込められている
- 豆知識③:稲羽山は現代の鳥取県にある‐和歌にも詠まれた名勝地




