百人一首の第39番は、参議等(さんぎひとし)が詠んだ、忍ぶ恋心を自然の風景と巧みに結びつけた歌として有名です。
百人一首『39番』の和歌とは
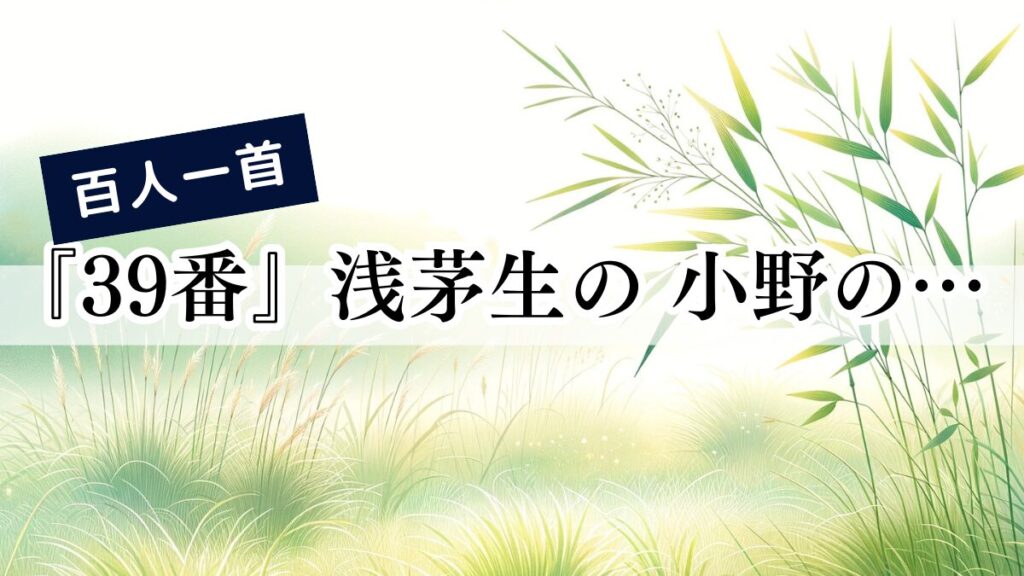
原文
浅茅生の 小野の篠原 しのぶれど あまりてなどか 人の恋しき
読み方・決まり字
あさぢふの おののしのはら しのぶれど あまりてなどか ひとのこいしき
「あさぢ」(三字決まり)
現代語訳・意味
まばらに茅(ちがや)が生えている野原の篠竹のように、忍んで恋を隠していましたが、それももう限界です。どうしてこれほどまでにあの人が恋しいのでしょうか。

背景
百人一首『39番』の和歌は、平安時代中期の歌人・参議等(さんぎひとし)による恋の歌です。
当時の貴族社会では恋心を公にすることは難しく、多くの恋が「忍ぶ恋」としてひそかに交わされていました。この歌では「浅茅生」や「篠原」という風景を用いて、隠しきれない恋心を表現しています。
また、『古今和歌集』の歌を踏まえた「本歌取り」という技法が使われており、過去の名歌の要素を活かしながら新たな情感を加えた一首です。こうした背景を知ることで、歌の情景や作者の心情がより深く伝わってきます。
語句解説
| 浅茅生(あさぢふ) | まばらに生えている茅(ちがや)のことを指します。背が低く荒れた野原に見られる植物です。 |
|---|---|
| 小野(おの) | 「小」は接頭語で特に意味はなく、「野」は野原を意味します。「小野」は小さな野原という表現です。 |
| 篠原(しのはら) | 細くて背が低い竹「篠竹(しのたけ)」が生えている野原です。序詞として「しのぶ」にかかっています。 |
| 忍ぶれど(しのぶれど) | 「忍ぶ」は「我慢する」「心の中に思いを秘める」という意味です。「れど」は逆接の助詞で、「~けれども」と訳されます。 |
| あまりて(あまりて) | 感情や思いが抑えきれずに溢れ出してしまう状態を表します。「我慢できないで」という意味です。 |
| などか(などか) | 疑問を表す副詞で、「どうして」という意味です。「なぜこのように」という問いかけの気持ちが含まれています。 |
| 人の恋しき(ひとのこいしき) | 「人」は恋の対象、「恋しき」は「恋しい」という意味です。全体で「どうしてあの人がこんなにも恋しいのだろう」と訳されます。 |
作者|参議等
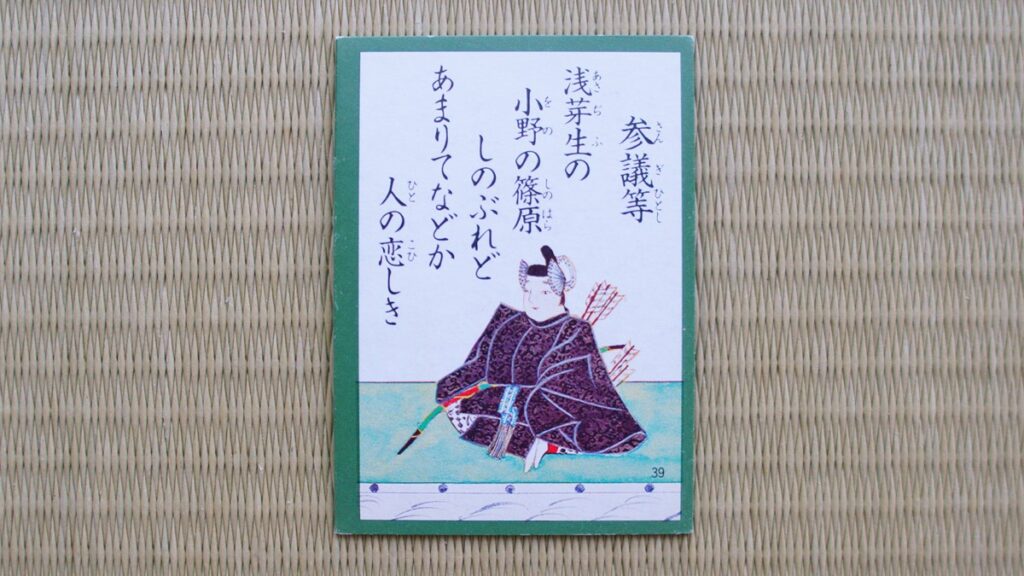
| 作者名 | 参議等(さんぎ ひとし) |
|---|---|
| 本名 | 源等(みなもとの ひとし) |
| 生没年 | 880年(元慶4年)〜951年(天暦5年) |
| 家柄 | 嵯峨天皇のひ孫で、貴族出身。父は中納言の源希(みなもとの のぞむ)。 |
| 役職 | 近江権少掾(おうみのごんのしょうじょう)を経て、左中弁、右大弁などを歴任。947年に参議に任命された。 |
| 業績 | 地方の守(守護)として三河守、丹波守、美濃権守、備前守を歴任し、最終的に参議として中央政界に登りつめた。 |
| 歌の特徴 | 自然の風景を背景にして、恋心や人間の感情を繊細に表現することが多い。特に、忍ぶ恋や切ない思いを美しい情景と結びつけて詠むのが特徴。 |
出典|後撰和歌集
| 出典 | 後撰和歌集(ごせんわかしゅう) |
|---|---|
| 成立時期 | 951年(天暦5年)頃 |
| 編纂者 | 梨壺の五人(なしつぼのごにん) |
| 位置づけ | 八代集の2番目の勅撰和歌集 |
| 収録歌数 | 1,425首 |
| 歌の特徴 | 日常的な贈答歌や人事を詠んだ歌が多く、権力者と女性とのやり取りが多く収録されています。公的な歌より私的な歌を重視し、柔らかく女性的な歌風が特徴です。 |
| 収録巻 | 「恋」578番 |
語呂合わせ
あさぢふの おののしのはら しのぶれど あまりてなどか ひとのこいしき
「あさぢ あまり(朝ジュースあまり)」
百人一首『39番』の和歌の豆知識

篠竹と恋心の「しのぶ」の関係
「篠原」とは背が低く、細い竹が生えている野原のことですが、この「しの」が「しのぶ」(我慢する、恋を秘める)の意味にかかっています。
このように、自然の風景を使って恋心を表現する技法を「序詞(じょことば)」といいます。この序詞によって、歌全体が繊細で美しいイメージを持つようになり、恋の切ない心情が巧みに表現されています。まるで篠竹が揺れるように、恋心も揺れているような描写が魅力的です。
本歌取りの技法
元となった歌は『古今和歌集』の中に収録されているもので、「浅茅生の 小野の篠原 しのぶとも 人知るらめや 言ふ人なしに」という歌です。この技法を「本歌取り」といい、先行する歌の一部を引用しながら、新しい感情や視点を加えて作り直します。
39番の歌では、恋心を表す表現がさらに豊かにされています。こうした和歌の技巧を知ると、より深く楽しめます。
参議等の影響力
当時は貴族や上流階級の人々が和歌を詠むことが文化的なステータスでした。参議等も、その流れの中で美しい和歌を多く残しましたが、特にこの歌は忍ぶ恋の心情を描きながら、自然との融合が見事な一作です。
政治的には目立たなくても、和歌で永遠に名を残すことができたという点も興味深いところです。
まとめ|百人一首『39番』のポイント
- 原文:浅茅生の 小野の篠原 しのぶれど あまりてなどか 人の恋しき
- 読み方:あさぢふの おののしのはら しのぶれど あまりてなどか ひとのこいしき
- 決まり字:あさぢ(三字決まり)
- 現代語訳:まばらに茅が生えている野原の篠竹のように恋心を忍んできたが、もう限界。なぜこれほどまでにあの人が恋しいのだろうか
- 背景:平安時代の貴族社会では恋愛を公にしにくく、ひそかに思いを忍ぶ恋が多かったため、その心情を詠んだ歌
- 語句解説①:浅茅生(あさぢふ)‐まばらに生えた茅(ちがや)のこと。背が低く荒れた野原に見られる
- 語句解説②:小野(おの)‐「小」は接頭語で意味はなく、「野」は野原の意味
- 語句解説③:篠原(しのはら)‐細く低い竹「篠竹」が生えている野原のこと
- 語句解説④:忍ぶれど(しのぶれど)‐「忍ぶ」は「我慢する」「心に秘める」という意味。「れど」は逆接の助詞
- 語句解説⑤:あまりて(あまりて)‐感情が抑えきれず溢れ出す状態。「我慢できないで」という意味
- 語句解説⑥:などか(などか)‐疑問を表す副詞。「どうして」の意味を持つ
- 語句解説⑦:人の恋しき(ひとのこいしき)‐「人」は恋の対象、「恋しき」は「恋しい」という意味
- 作者:参議等(さんぎひとし)
- 作者の業績:三河守、丹波守、美濃権守、備前守を歴任し、最終的に参議として中央政界に進出
- 出典:後撰和歌集(ごせんわかしゅう)
- 出典の収録巻:恋・578番
- 語呂合わせ:あさぢ あまり(朝ジュースあまり)
- 豆知識①:篠竹と恋心の「しのぶ」の関係‐「篠竹(しのたけ)」の「しの」が「しのぶ」(恋を秘める)の意味にかかっている
- 豆知識②:本歌取りの技法‐『古今和歌集』の「浅茅生の 小野の篠原 しのぶとも 人知るらめや 言ふ人なしに」をもとに新たな表現を加えた
- 豆知識③:参議等の影響力‐政治的な権力は大きくなかったが、百人一首に選ばれるほどの優れた歌人として名を残した




