百人一首の第59番は、作者 赤染衛門(あかぞめえもん)が詠んだ、待つ女性の切ない心情を美しく表現した歌として知られています。
百人一首『59番』の和歌とは
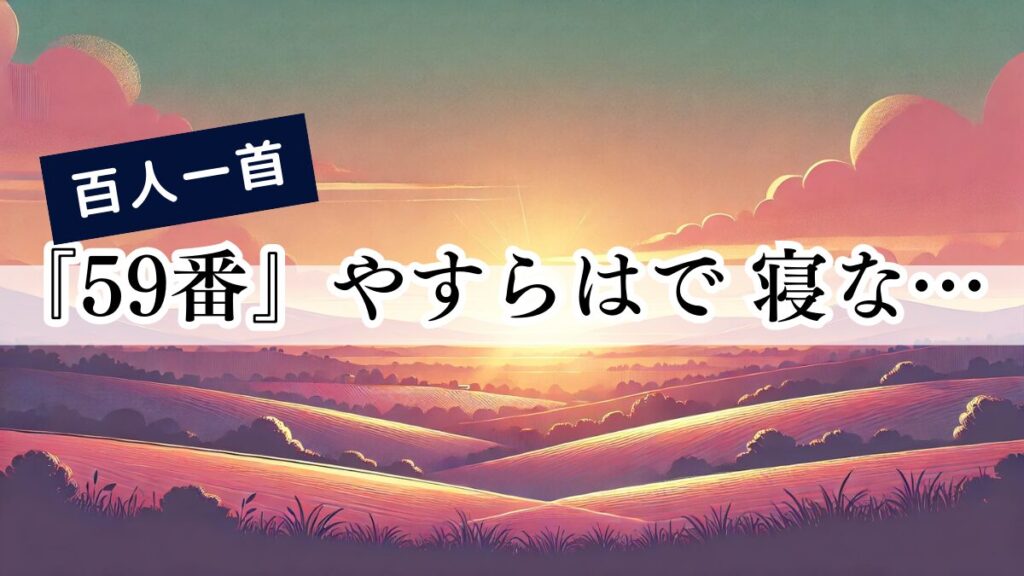
原文
やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて かたぶくまでの 月を見しかな
読み方・決まり字
やすらわで ねなましものを さよふけて かたぶくまでの つきをみしかな
「やす」(二字決まり)
現代語訳・意味
あなたが来ないとわかっていたなら、ためらわずにさっさと寝てしまえばよかったのに。待ち続けるうちに夜が更けてしまい、とうとう西の空に沈もうとする月を見ることになってしまいました。

背景
百人一首『59番』は、平安時代の歌人・赤染衛門が詠んだ恋の歌です。この歌は、当時の男女の恋愛事情が色濃く反映されています。
平安時代の貴族社会では「通い婚」という文化があり、男性が夜に女性のもとを訪れ、一夜を共にするのが一般的でした。しかし、約束をしたにもかかわらず男性が来なかった場合、女性は長い夜を待ち続けることになります。
この歌は、そんな切ない夜の心情を描いたものです。背景には、藤原道隆が赤染衛門の姉妹に「今夜訪れる」と約束しながら現れなかったというエピソードがあります。赤染衛門は、姉妹の代わりにこの歌を詠み、淡々とした言葉の中に、待つ女性の寂しさや少しの怒りを込めました。
語句解説
| やすらはで | ハ行四段活用動詞「やすらふ」の未然形で、「ためらう」「ぐずぐずする」の意味。打消の接続助詞「で」が付いて「ためらわずに」という意味になります。 |
|---|---|
| 寝なましものを | 「寝なまし」は、「寝る」という動詞に反実仮想の助動詞「まし」が付いた形。「寝てしまえばよかったのに」という後悔の気持ちを表現しています。「ものを」は逆接の接続助詞で、「~だろうに」というニュアンス。 |
| さ夜ふけて | 「さ」は調子を整えるための接頭語で、意味はありません。全体で「夜が更けていった」という意味になります。 |
| かたぶくまでの | 「かたぶく」は「傾く」の意味で、ここでは月が西に沈むことを指します。「まで」は限界や程度を示す助詞で、「月が西に沈む時まで」となります。 |
| 月を見しかな | 「かな」は詠嘆の終助詞で、「~だなあ」と感嘆の意を表します。全体で「月を見たなあ」という意味になります。 |
作者|赤染衛門
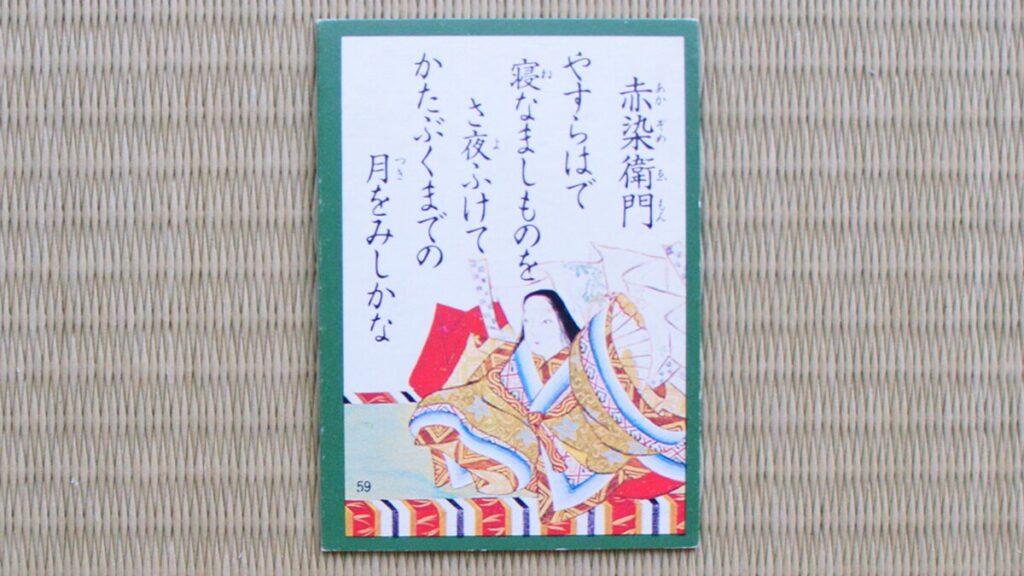
| 作者名 | 赤染衛門(あかぞめえもん) |
|---|---|
| 本名 | 不明 |
| 生没年 | 956年(天暦10年)頃 ~ 1041年(長久2年)頃 |
| 家柄 | 父は右衛門尉の赤染時用、または平兼盛とする説もあり、貴族階級の出身。 |
| 役職 | 藤原道長の正妻・倫子やその娘・彰子に仕える女房。 |
| 業績 | 「栄花物語」の作者とされる説がある。三十六歌仙、女房三十六歌仙に選ばれる。 |
| 歌の特徴 | 温厚で真摯な人柄が反映された、明瞭で品格のある歌風。恋や宮廷生活を題材にした、わかりやすく優美な表現が多い。 |
出典|後拾遺和歌集
| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |
|---|---|
| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |
| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |
| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |
| 収録歌数 | 1,218首 |
| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |
| 収録巻 | 「恋五」680番 |
語呂合わせ
やすらわで ねなましものを さよふけて かたぶくまでの つきをみしかな
「やす かたぶく(安い買った服)」
百人一首『59番』の和歌の豆知識

「待つ女性」の切ない夜
当時の恋愛では、男性が女性のもとへ夜に訪れることが一般的でした。しかし、約束が破られた場合、女性は夜通し待ち続けることになります。
この歌の女性も、待ち続けた末に夜が更け、西に傾く月を見上げることになりました。「来ないなら、さっさと寝てしまえばよかったのに」という言葉には、待ち続けた時間への切なさや虚しさが込められています。
作者は「代筆の名人」だった?
藤原道隆が赤染衛門の姉妹に「今夜訪れる」と約束したものの現れず、その後、姉妹に代わって赤染衛門が詠んだ歌なのです。
代筆とは思えないほど、待つ女性の気持ちがリアルに表現されています。当時の貴族社会では、こうした代筆の文化も重要な役割を果たしていました。
赤染衛門の読み方は?
「赤染」という苗字は父親の官職「右衛門尉」に由来し、「衛門」もそこから取られたものです。
赤染衛門は平安時代中期の女流歌人で、文学的な才能だけでなく、温厚な性格でも知られていました。彼女は藤原道長の正妻である倫子やその娘の彰子に仕え、宮廷で活躍しました。
同時代に活躍した紫式部や和泉式部とも交流があり、歌才を認められていました。読み方を知ることで、彼女の背景や和歌に込められた感情がより身近に感じられるでしょう。
まとめ|百人一首『59番』のポイント
- 原文:やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて かたぶくまでの 月を見しかな
- 読み方:やすらわで ねなましものを さよふけて かたぶくまでの つきをみしかな
- 決まり字:やす(二字決まり)
- 現代語訳:あなたが来ないとわかっていたなら、ためらわずにさっさと寝てしまえばよかったのに。待ち続けるうちに夜が更けてしまい、とうとう西の空に沈もうとする月を見ることになってしまった
- 背景:平安時代の「通い婚」において、男性が約束を破って来なかった女性の心情を詠んだ恋の歌
- 語句解説①:やすらはで‐「やすらふ(ためらう・ぐずぐずする)」の未然形+打消の「で」で「ためらわずに」の意味
- 語句解説②:寝なましものを‐「寝なまし」は反実仮想の助動詞「まし」が付き、「寝てしまえばよかったのに」と後悔を表す。「ものを」は逆接の助詞
- 語句解説③:さ夜ふけて‐「さ」は調子を整える接頭語で意味はなく、「夜が更けていった」の意
- 語句解説④:かたぶくまでの‐「かたぶく」は「傾く」の意味で、ここでは月が西に沈むこと。「まで」は限界を示し、「月が沈む時まで」の意
- 語句解説⑤:月を見しかな‐「かな」は詠嘆の終助詞で、「月を見たなあ」という感嘆の意味
- 作者:赤染衛門(あかぞめえもん)
- 作者の業績:「栄花物語」の作者とされる説がある。三十六歌仙・女房三十六歌仙に選ばれ、明瞭で品格のある歌風で知られる
- 出典:後拾遺和歌集
- 出典の収録巻:恋五・680番
- 語呂合わせ:やす かたぶく(安い買った服)
- 豆知識①:「待つ女性」の切ない夜‐平安時代の「通い婚」において、約束を破られた女性が待ち続ける寂しさや虚しさを表現した歌
- 豆知識②:作者は「代筆の名人」だった?‐この歌は赤染衛門の姉妹のために詠まれたとされ、当時の貴族社会では代筆が一般的だった
- 豆知識③:赤染衛門の読み方‐読み方は「あかぞめえもん」。「赤染」という苗字は父親の官職「右衛門尉」に由来




