百人一首の第60番は、小式部内侍(こしきぶのないし)が詠んだ、優れた歌才を証明するエピソードと共に知られる一首です。
百人一首『60番』の和歌とは
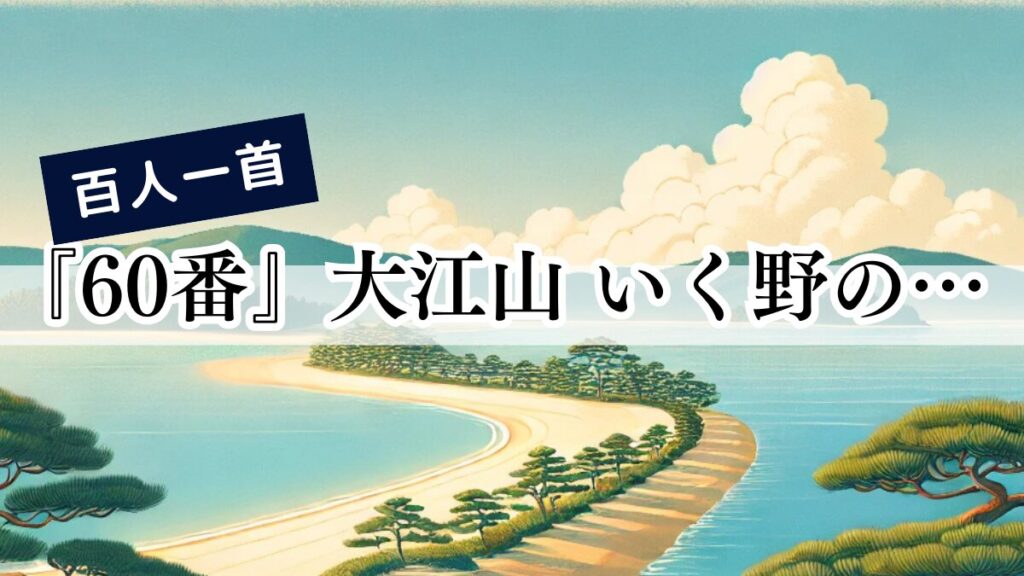
原文
大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立
読み方・決まり字
おおえやま いくののみちの とおければ まだふみもみず あまのはしだて
「おおえ」(三字決まり)
現代語訳・意味
大江山を越え、生野を通る丹後への道は遠すぎて、まだ天橋立の地を訪れたこともなければ、母からの手紙も見ていません。

背景
小式部内侍が詠んだこの歌は、当時の和歌会(歌合)での出来事が背景にあります。
母である和泉式部が丹後に滞在していたことから、小式部内侍の歌が「母の代作ではないか」と噂されていました。ある日、藤原定頼がその疑惑をからかうように「母親に代作を頼むために使者を送ったのか?」と問いかけました。それに対して小式部内侍は、即興でこの歌を詠み、自分の才能を証明しました。
このエピソードは、小式部内侍の聡明さと機転の良さを示すものとして有名です。また、この歌には「大江山」「生野」「天橋立」などの地名が巧みに取り入れられ、掛詞や縁語が用いられています。
語句解説
| 大江山(おおえやま) | 京都府西京区にある大枝山のこと。丹波国北部の大江山(鬼退治で有名)とは異なる山です。 |
|---|---|
| いく野の道(いくののみち) | 京都府福知山市にある生野(いくの)の地名を指し、「野を行く」の「行く」との掛詞になっています。 |
| 遠ければ(とおければ) | 「遠いので」という意味。形容詞「遠し」の已然形に接続助詞「ば」をつけた表現です。 |
| まだふみも見ず(まだふみもみず) | 「ふみ」に「踏み(地を踏む)」と「文(手紙)」を掛けた掛詞。「地を踏んだこともなければ、手紙も見ていない」という二重の意味を表します。 |
| 天の橋立(あまのはしだて) | 京都府宮津市にある名勝で、日本三景のひとつ。地名そのものが歌の題材になっています。 |
作者|小式部内侍
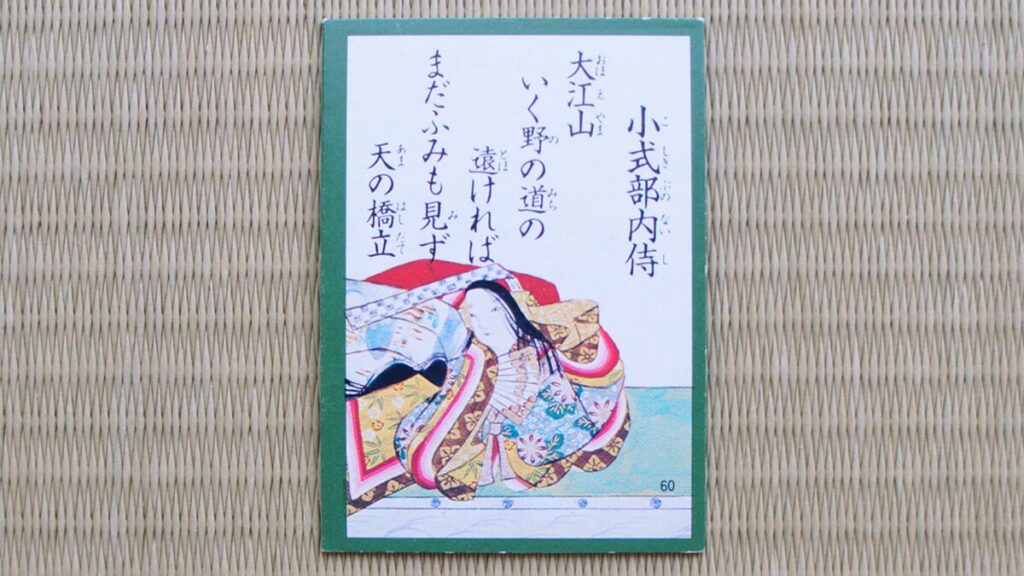
| 作者名 | 小式部内侍(こしきぶのないし) |
|---|---|
| 本名 | 不明 |
| 生没年 | 999年(長保元年)頃 ~ 1025年(万寿2年) |
| 家柄 | 父:橘道貞(たちばなのみちさだ)、母:和泉式部(いずみしきぶ)。平安時代中期の有力な歌人の家庭に生まれる。 |
| 役職 | 一条天皇の中宮・彰子(しょうし)に仕えた女房。 |
| 業績 | 若年ながら、天才的な歌才を発揮し、母和泉式部に匹敵するほどの評価を得た。女房三十六歌仙の一人。 |
| 歌の特徴 | 言葉の掛け合わせ(掛詞)や連想技法(縁語)を巧みに使用。感情や状況を洗練された表現で詠む点が特徴的。 |
出典|金葉和歌集
| 出典 | 金葉和歌集(きんようわかしゅう) |
|---|---|
| 成立時期 | 1127年(大治2年)頃 |
| 編纂者 | 源俊頼(みなもとのとしより) |
| 位置づけ | 八代集の5番目の勅撰和歌集 |
| 収録歌数 | 約650首 |
| 歌の特徴 | 新奇な表現や自然観照、田園趣味を重視。巻末に連歌を加えた革新性が特徴で、当代歌人の歌が多く収録されています。 |
| 収録巻 | 「雑上」550番 |
語呂合わせ
おおえやま いくののみちの とおければ まだふみもみず あまのはしだて
「おおえ まだ(大江山をまた覗き)」
百人一首『60番』の和歌の豆知識

小式部内侍は「即興の天才」だった!?
和歌を作るには時間がかかるものですが、彼女はその場で考え、しかも巧みな掛詞や地名を使いながら、母の代作疑惑を一瞬で払拭しました。当時の和歌会では、即興で美しい歌を詠むことができるのは非常に高い才能の証とされていました。
さらに、彼女がまだ10代半ばであったことを考えると、その才能の非凡さがわかります。藤原定頼も、予想外の切り返しに驚き、返歌もできずにその場を去ったと伝えられています。この出来事が、小式部内侍を語るうえで欠かせない逸話となり、後世にも語り継がれることになりました。
「ふみ」の掛詞が生んだ名作!
当時の和歌では、一つの言葉に複数の意味を持たせる「掛詞」という技法がよく使われましたが、この歌はその中でも特に美しく、意味深い表現とされています。
「踏み」は「天橋立の地を踏んだことがない」という意味、一方で「文」は「母からの手紙を見ていない」という意味になります。さらに、「踏み」は「橋」とも関連があるため、「天の橋立」という場所とのつながりも強まります。このように、一つの言葉で多くの意味を持たせることで、短い歌の中に深いメッセージを込めることができるのです。
「大江山」は鬼退治の伝説の地?
「大江山」と聞くと、多くの人が鬼退治の伝説を思い浮かべるかもしれません。実際、平安時代には源頼光とその家臣たちが、鬼の頭領・酒呑童子(しゅてんどうじ)を退治したという伝説があります。しかし、この歌に出てくる「大江山」は、鬼伝説で有名な京都府北部の大江山ではなく、現在の京都市西京区にある「大枝山(おおえやま)」と考えられています。
道順を考えると、丹後へ行くにはこの大枝山を越えるルートが一般的だったため、小式部内侍はこの地名を使いました。このように、同じ名前の山でも別の場所を指していることは、和歌を理解するうえで重要なポイントになります。
まとめ|百人一首『60番』のポイント
- 原文:大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立
- 読み方:おおえやま いくののみちの とおければ まだふみもみず あまのはしだて
- 決まり字:おおえ(三字決まり)
- 現代語訳:大江山を越え、生野を通る丹後への道は遠すぎて、まだ天橋立の地を訪れたこともなければ、母からの手紙も見ていない
- 背景:小式部内侍が和歌会で母の代作疑惑をかけられ、それを否定するために即興で詠んだ歌
- 語句解説①:大江山‐京都府西京区にある大枝山を指す。鬼退治で有名な丹波の大江山とは別の山
- 語句解説②:いく野の道‐京都府福知山市にある生野の地名。「野を行く」と「生野」の掛詞になっている
- 語句解説③:遠ければ‐「遠いので」という意味。形容詞「遠し」の已然形+接続助詞「ば」
- 語句解説④:まだふみも見ず‐「踏み(地を踏む)」と「文(手紙)」の掛詞で、まだ天橋立に行ったことも手紙を見たこともないことを表す
- 語句解説⑤:天の橋立‐京都府宮津市にある名勝で、日本三景の一つ
- 作者:小式部内侍(こしきぶのないし)
- 作者の業績:若くして天才的な歌才を発揮し、女房三十六歌仙の一人として名を残した
- 出典:金葉和歌集(きんようわかしゅう)
- 出典の収録巻:雑上・550番
- 語呂合わせ:おおえ まだ(大江山をまた覗き)
- 豆知識①:小式部内侍は「即興の天才」‐母の代作疑惑を皮肉られた際、数秒でこの歌を詠み、才能を証明した
- 豆知識②:「ふみ」の掛詞が生んだ名作‐「踏み」と「文(手紙)」の二重の意味を持ち、天橋立との関連もある技巧的な表現
- 豆知識③:「大江山」は鬼退治の伝説の地?‐有名な鬼退治の大江山とは異なり、京都府西京区の大枝山を指す




